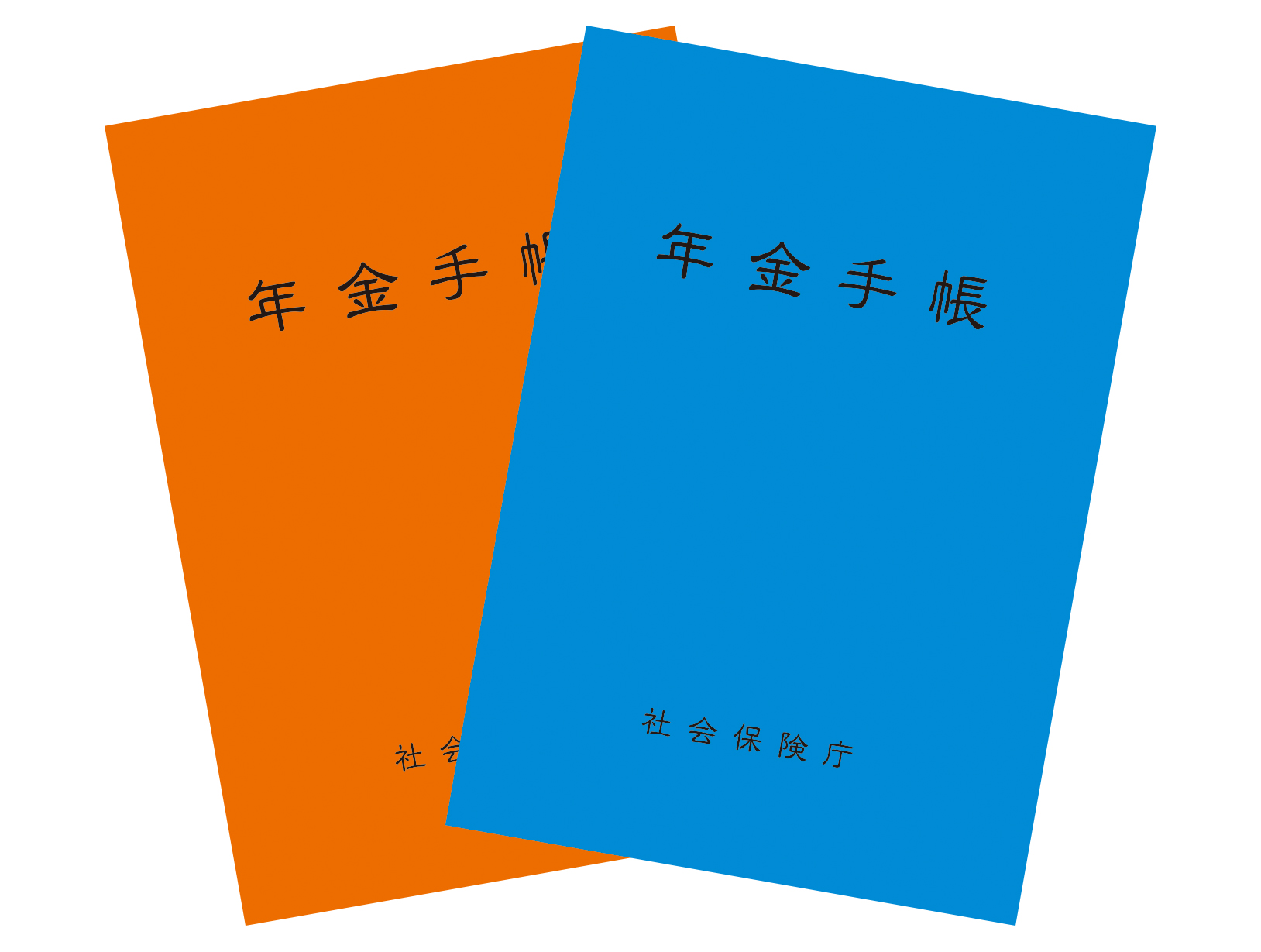
年金がいくらもらえるかご存知ですか?
今回は将来、自分が年金をどのくらいもらうことが出来るのかという話をしたいと思います。日本の公的年金は現在、2種類の制度があります。「国民年金」と「厚生年金」です。「国民年金」は原則として20歳から60歳になるまでの全ての国民が加入し、「厚生年金」には会社員や公務員等に勤務されている方が加入することになっています。この時、「厚生年金」に加入している人は「国民年金」に同時加入の扱いとなります。
将来一定の年齢(現段階では65歳)になると、「国民年金」の納付記録から計算した「老齢基礎年金」がもらえ、「厚生年金」に加入したことがある人は、「老齢基礎年金」に上乗せして「厚生年金」の加入記録から計算した「老齢厚生年金」がもらえる、という仕組みになっています。年金の仕組みは複雑でわかりにくいものですが、まず知りたいところが「いくらくらいもらえるのか」ということでしょう。ここから「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」それぞれの金額がどのくらいになるのかをざっくりとみていきたいと思います。
老齢基礎年金の計算方法
「老齢基礎年金」の計算方法を説明します。「老齢基礎年金」は、原則として65歳からもらえ、原則10年以上の期間、年金保険料を払い込んだ人は誰もがもらえることになっています。「国民年金」の納付可能期間である20歳から60歳になるまでの40年間、480ヵ月について、全部納付をすれば満額が得られ、納付していない期間があれば、その割合に応じて減額される、という仕組みをとっています。ちなみに、満額の老齢基礎年金は、年額約78万円となっています。
納付月数とは、❶国民年金保険料を納付した期間、❷20歳から60歳になるまでの間で厚生年金に加入した期間、❸20歳から60歳になるまでの間で厚生年金に加入している配偶者の扶養に入っていた期間について、該当するものを合計したものとなります。
また「国民年金保険料」が納付できない事情がある場合は、保険料の全部または一部の支払いが免除されることがあります。この場合は免除を受けた月数に定められた換算割合をかけ、納付月数にプラスすることになっています。
老齢厚生年金の計算方法
「老齢厚生年金」の計算方法をみていきましょう。「老齢厚生年金」は、原則として10年以上年金保険料を支払い、「老齢基礎年金」を受ける権利がある人であれば、「厚生年金」の加入自体は1ヶ月でも、その分に応じて受けることができます。この計算は、平均報酬額と加入月数で計算します。平均報酬額については、一度、制度変更があり、それ前と後では少し異なります。一般的に、会社等に長く勤務することで、金額も多くなります。
B=平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 平成15年4月以降の加入月数
A+B=「老齢厚生年金」の年金額
平均標準報酬額の方にはボーナスも含まれ、ボーナスも加えた報酬月額となります。実際にはこの計算のほか、生年月日に応じた例外があったり、過去の給与額を現在の物価に引き直したりするので、とても複雑な計算となりますが、ざっくりと計算する場合、45歳の給与をベースに計算してみると良いと思います。45歳未満の方は、年間の昇給率を2%として計算してみてください。入社時の年齢と65歳で定年することを勘案して、加入月数を算出してみて下さい。この2つの数値を使い計算してみて下さい。それから、平成15年の制度変更は無視して下さい。実際に貰える年金金額とは少し異なるかもしれませんが、大体の目安にはなると思います。
加給年金と振替加算
この「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」に加え、加算される年金があります。一定の条件を満たした配偶者や子を扶養している場合、老齢厚生年金に加算を受けることができる加給年金、配偶者の加給年金が終了した後、一定の条件を満たせば加給年金打ち切り後に扶養されている側の年金に少額の加算が受けられる振替加算などがあります。
年金額を把握して老後の計画を
このように、実際に自分は年金をいくらもらえるのかを把握すると、老後の資金設計の必要性を少し実感して頂けると思います。ただお金を貯めるだけではなく、運用する必要性も感じて頂けるかと思います。お金の運用に関しては、日本ではギャンブルと同一化されている感じもあり、泡銭という印象を持たれがちですが、諸外国では、自らの資金を運用することが一般的に行なわれています。ぜひそういった視点も持って頂きたいと思います。














